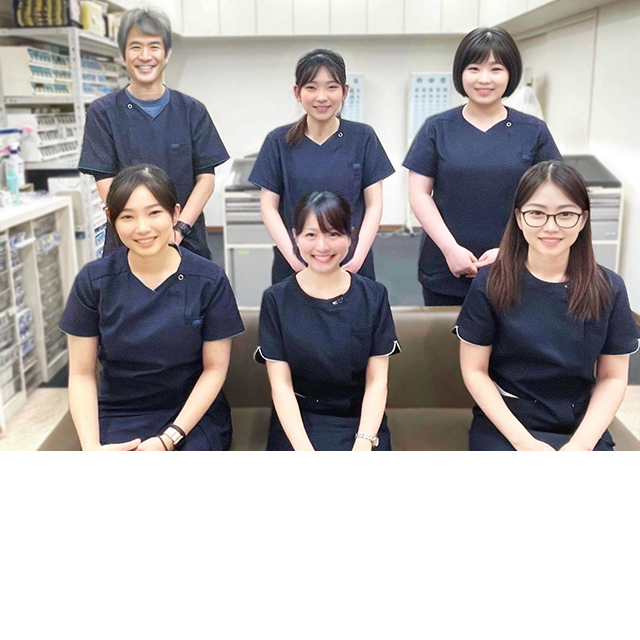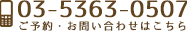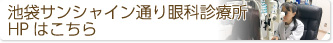307:ドライアイの検査について
ドライアイは、涙液の分泌が少なかったり、または、涙液の安定性が悪いことから、角膜が乾燥して角膜が傷付いたり不快な症状が生じる疾患です。日本では800万人以上もの多くの方がドライアイで悩まされていると推定されており、特にコンピュータを使う現代人や、高齢者、女性に多い傾向にあります。ドライアイの診断には、眼科でいくつかの検査を行う必要があります。
・シルマー試験
シルマー試験とは、涙の分泌量を調べるドライアイの検査です。規格に合った細い濾紙(ろし)を瞼に挟み、5分間で濾紙がぬれる長さを測定します。10mm以上が正常ですが、5mm以下の場合には、ドライアイが疑われます。
・BUT測定(涙液層破壊時間測定)
BUT測定とは、目の表面を覆っている涙が、どのくらいの時間で乾燥し始めるかを調べる検査です。フルオレセインという色素を点眼し、細隙灯顕微鏡で青色光を用いて目の表面を観察すると、涙に混ざった色素が黄色に見えます。まばたきを止めて、真っすぐ正面を見ていると、次第に目の表面が乾いて色素が消える部分が出現します。この時間をBUT(Tear Break Up Time)と呼び、10秒以上が正常ですが、5秒以下なら、ドライアイが疑われます。
・生体染色検査
目の表面が非常に乾燥すると、黒目の表面(角膜)や白目の表面(結膜)に障害を起こします。特殊な色素を点眼して細隙灯顕微鏡で観察すると、障害を生じた部分が染まって見えます。色素には、前述のフルオレセインや、ローズベンガルという濃いピンク色の色素を用いることもあります。
・ティアメニスカス検査
涙液の量を調べるため、フルオレセインを目に入れ、下瞼にどれだけ涙が溜まっているか細隙灯顕微鏡を使って観察します。分泌された涙はまず下瞼に溜まった後、目全体に広がっていく性質を利用する検査です。涙点プラグなどの治療を行った後、どれだけ涙液が目に留まるようになったか効果を確認する際にも用いられます。
ドライアイの患者様は年々増え続けています。ドライアイの症状を改善するには、まずは点眼治療から始めていただき、それでも良くならなければ涙点プラグなども治療法もございますので、お気軽にご相談ください。